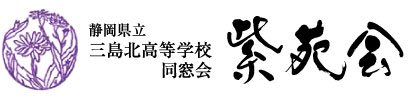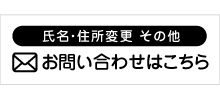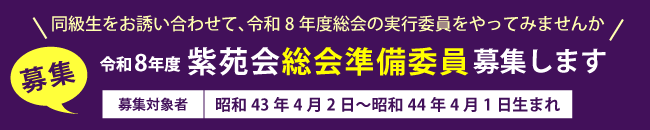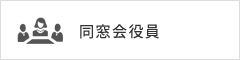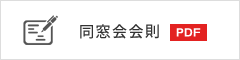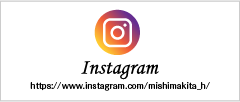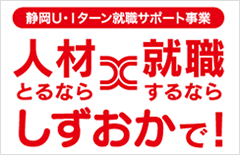会長あいさつ
母校の発展を期して
静岡県立三島北高等学校同窓会
紫苑会会長 鈴木愛子
私たちの母校、静岡県立三島北高等学校は、明治34年に現在の三島駅南口一帯に在った小松宮彰仁親王殿下の別邸の一部をお借りして、「静岡県田方郡立三島高等女学校」として開校しました。
遡ること150余年、明治新政府は、国民の知識を高め国家の近代化を進めることを目指して6歳以上の男女すべてに身分に関係なく教育を受けさせることを決め、明治5年に学制を発布しましたが、当時は未だ多くの人々の生活は貧しく、一軒の家では男子は学ぶことができたとしても女子は家事労働や農作業などの手伝いに追われ、なかなか「学校」へ通うことは叶わなかったようです。
そこには「おなごに教育は要らない」という根深い考えもありました。そうした世相の中でも、当地はその昔三島宿として栄えていたこともあり、幸いなことに教育に対する意識の高い篤志家も多くいましたので、それらの方々が「この地に女学校の設立を」と各方面に働きかけご尽力くださったお陰で、学制発布から遅れること30年、ようやく開校することができました。その後、大正11年には大宮町に移転し「静岡県立三島高等女学校」となりましたが、昭和23年の学制改革により新制高等学校「静岡県立第一高等学校」として発足し新たに定時制夜間過程が開設され、翌年の昭和24年には「静岡県立三島北高等学校」へと改称し定時制を含めた男女共学制を実施しています。昭和32年に現在地三島市文教町に校舎を新築し移転、素晴らしい環境の中で学校施設も立派に拡充されていき、平成16年からは全日制普通科男女共学校となっています。このように開校から125年に亘り公立高等学校として、校訓「自律」のもと時代に対応しながら女子教育や社会に有意な人材の育成を目標に掲げ歩んでまいりましたが、この間には関東大震災や北伊豆地震で校舎や寄宿舎が損壊してしまったり、戦争末期の昭和20年には授業を一年間停止し、校舎内では兵器を作り、運動場は掘り返して芋畑麦畑となったりするなど苦難の数々もありました。しかし「どのように厳しい状況下にあっても、先生方は常に最善の方策で生徒を守り鼓舞して下さった」と記録にあります。その教育の精神は、現在も脈々と受け継がれ、校長先生をはじめ先生方は凛として生徒の教育に熱心に取り組んでくださっています。そうした先生方や地域の方々にも見守られ、今も昔も変わらず明るくのびのびと学校生活を謳歌する生徒達の姿に、同じ学窓を巣立ったものとしてこれまでの感謝と将来への希望が湧いてまいります。
学校創立から3年後の明治37年に設立された同窓会も120余年の歴史を刻み、国内はもとより海外も含め29,000人もの同窓生を数えるまでになりました。諸先輩方には長年にわたり、同窓の絆を深め、労をいとわず同窓会「紫苑会」の活動を継続いただきましたことに感謝申し上げます。紫苑会が数多の卒業生の皆様と共にあって、このような歴史と伝統を備えた母校の益々の発展を願い、そこに学ぶ生徒達の学校生活を支える務めを果たせますことに大きな意義と誇りを感じます。引続き、皆様方には紫苑会の活動にご理解ご協力をお願いいたしますとともに、ご活躍を心よりご祈念申し上げます。
この度、25年ぶりの改訂を行い、「紫苑会会員名簿」を発行いたしました。これは、紫苑会の歴史の重みと恒久的な発展を担い、新たに入会する卒業生と現在会員である皆様をつなぐための会務の執行にあたって正確な会員名簿の必要性の高まりを受け、会則に則り慎重な検討を重ねて実現したものです。実際の改訂・発行業務にあたっては、近く3万人にもなんなんとする方々の名簿整理・調査・発送作業等々はとても紫苑会役員の手には負えないものと判断し、民間事業者に委託いたしました。名簿への掲載希望の有無、記載内容等につきましては、事前に会員ご自身に十分な確認作業を行った上で改訂・発行されています。これにより紫苑会の活動が益々充実したものとなり、皆様方の絆がさらに深まりますことを願っております。